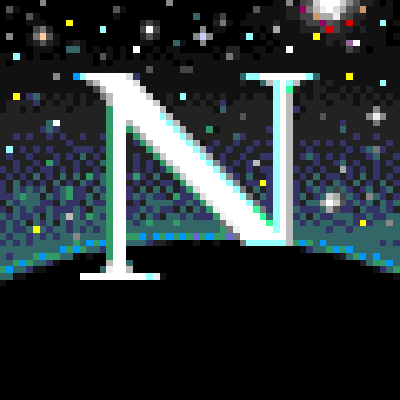
何も考えず、感情の起伏もなく、
一日を過ごすのが本当の休日だとすれば…
毎日が休日か?
“実写にしか見えない”伊藤園「AIタレント」の衝撃 なぜ注目されたのか
未知への不安を抱きやすい人ほど、分類困難な対象を不気味と感じやすいことを明らかにしている。未知のものを回避しようとする心理が不気味の谷現象を生み出しているといえるだろう 。
NISA
アエラドットに新NISA「つみたて投資枠」で買える投信の条件についてめちゃめちゃ詳しい記事あり
新しいNISA制度の生涯投資枠1800万円を「つみたて投資枠」の商品と「成長投資枠」の商品に分けて投資する必要は全くありません。
私自身も「つみたて投資枠」対象のオルカンだけで生涯投資枠1800万円を埋める予定です。
詳しいなと思ったのは、金融庁指定のインデックスを12本明記して、それ以外のインデックス(例えばNYダウ)に連動するものは、たとえインデックスファンドであっても右側の指定インデックス投資信託以外の投資信託(アクティブ運用投資信託など)に分類され、そちらの条件が適用されることまで明記されていることです。
金融庁指定インデックス
| 日本市場 | TOPIX 日経平均 JPX日経400 |
| 全世界 | MSCI ACWI Index FTSE Global All Cap Index |
| 先進国 | MSCI World Index = MSCIコクサイ FTSE Developed All Cap Index |
| 米国市場 | S&P 500 CRSP U.S. Total Market Index → CRSP全米株式指数 |
| 新興国 | MSCI Emerging Markets Index FTSE Emerging Markets Index FTSE RAFI Emerging Index |
定額減税と総選挙の看板
定額減税が4万円で、5兆円規模とは予想外だった。減税の効果が現れるのは夏くらいになるが、その頃に総選挙なら十分なのだろう。
「減税」は、やめた時点で一気に5兆円の緊縮になるから、1回限りでは済まず、縮小しつつ着地するプランが必要だ。それは総選挙時の看板施策になる。
来年は、少子化が止まらない数字が出る中で、厚生年金の財政検証かあり、年金改革が焦点になる。合理的に考えれば、恒久的な給付制度を足がかりに、勤労者皆保険を実現し、年金水準の低下を防ぐという選択になる。十分に選挙の看板になるもの
ノーラン監督作『オッペンハイマー』日本公開の行方と意義
ノーラン史上最高傑作
Varietyの「日本公開は東宝東和にかかっている」という主張が、現時点では事実ではないことがわかった。また、一部の報道やSNSなどでささやかれてきた「日本サイドが難色を示している」との情報は、その信憑性を保証する根拠を確認できなかった。
さらに、固有名詞を挙げることは避けるが、日本での配給・公開に関して、国内で新たにポジティブな動きを確認できている。ただし、現時点で具体的なことは未定の状況という。確かな情報は今後の正式発表を待ちたい。
映画の原作となったカイ・バード&マーティン・J・シャーウィン著『オッペンハイマー』も、2024年1月10日に早川書房(ハヤカワ・ノンフィクション文庫)より復刊される。編集担当の山本純也氏によると、文庫化の企画は映画の製作が発表された約2年前から動き出しており、日本公開をめぐる状況を考慮したものではないという。
むしろ本作の肝は、物事の肯定・否定、描写の適切・不適切という二項対立では論じきれない複雑さにあるとも感じた。そもそも映画の主題は、原子爆弾ではなくオッペンハイマーの半生なのだ。
自ら脚本を執筆したノーランは、物語の大部分をオッペンハイマーの視点から描いた。脚本のト書き(※台詞以外の動作や描写)まで主語を「私(I)」にするほどの徹底ぶりで、広島・長崎への投下を直接描かなかったのも、現実のオッペンハイマーがその事実をラジオで知ったからだと説明されている(*3)。あくまでも「オッペンハイマーが何を見て、何を感じ、何を考えたのか」に焦点を合わせた構成だ。
ガンガル
twitter.comイエサブさんのコンテスト
— ぽん☆ぽこ (@onaka_ponpoco_) October 29, 2023
ちゃっかり入賞してました〜♪
現地で見て頂いた皆様、投票して頂いた皆様ありがとうございました‼️
もう少し展示させて頂きますので、ご来店の際に見てやって頂けると嬉しいです🤤 https://t.co/lIHTZlpF5y
ガンプラ・ブームに便乗した商品として、よく理解していない大人が子供に買い与えそうな悲劇を連想させて、その存在自体について、個人的には良い印象を持っていない。
それが時を経て、いわゆる「コレジャナイ」のようなネタ、懐古趣味的な観点からは許容される存在になった。
『ガンダム・センチネル』以降のグラフィック・デザイン的なアレンジ、一見、イラストのように見える騙し絵、二次元的な塗装表現、『アトランジャー』のようなオリジナル・ロボットをMGシリーズのような現代的にアレンジする試み、などなど
そのような存在も受け入れてしまうプラモデル界隈には、何でも取り込んでしまう包容力、それは貪欲さを通り越して、包摂すら感じさせる、健全な進化、発展の証左なのだろう。何でも楽しんでしまう、楽しもうとする姿勢が清々しい。