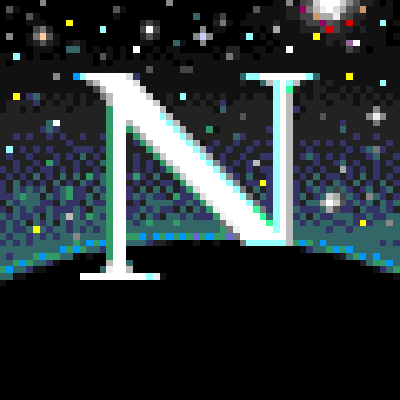
考えることを疎かにし続けている。
だから考える時間を確保しないばかりか、
そのような時間を確保することすら意識していない。
意識したとしても元が疎かだから、
確保した時間を浪費してしまう。
「未婚者は"幸福度が低い"」調査の裏側にある真実
既婚者と未婚者とでそれぞれの幸福度を調査すると、男女年代別にかかわらずすべて既婚者のほうが未婚者より幸福度は高いものになります
未婚男性の幸福人口は年代があがるごとに大きく絶対数が減ります。これは、幸福な未婚者が結婚して未婚から既婚へと変わっていっているため、幸福な未婚人口が減っているわけです。
つまり、未婚が既婚より不幸なのではなく、もともと幸福な未婚が結婚して既婚となるから、結果として既婚の幸福人口が多くなっているというだけなのです。
どのような状態が幸福であるかは人それぞれだろう。不幸も同様であるはずだ。
よくわからないのが、自分が不幸であるとする理由だ。何をして幸福とするか、未婚男性の幸福人口が年代が上がるごとに減少するからと言って、不幸とする原因の一つが未婚だとしても、それだけが決定要因とは思えない。
年代が上がるごとに、幸福人口に含まれる未婚者が増え、未婚者の幸福人口が減少していく。その結果、年代が上がるごとに、未婚者全体に占める不幸人口が相対的に増えていく、ということを記事では主張している。
しかし不幸の原因が何か分からないのだから、「だからどうした」という感想しかない。
その点を明らかにせず、
- そもそも幸福でなければ結婚したいとも思わない
- 若者は幸福でないから、結婚したいと思わない
- 若者が幸福でないのは、金がないから
という観点から記事は、論を続ける。
現在の若者に限らず、基本的にいつの時代でも裕福な若者は少数派であるはずだ。この前提では、いつの時代においても、若者は幸福ではないし、結婚したいとも思わないことになる。特に現在の若者について、お金がないこと以外の不幸要因として、将来に対する不安を挙げている。将来、好転する見込みがないのだからリスクを避けたい。それが若者を無行動に向かわせる。結婚しないことも、その無行動に含まれている、という論だ。
そこで、若者が行動できるようにするお膳立てとして、次の結論に至っている。
お金がすべてだとまでは言いませんが、行動するにもお金は必要です。
お金が必要なのは間違いない。お金を持つことで、行動の幅も広がることだろう。しかし、その結果が幸福とは限らないのではないか。今よりマシにはなるだろうが、それが幸福となる決定打とも思えない。
80年代バブルの時代、同様にお金は持たずとも、現在の若者に比べて、当時の大学生の社会的な経済状況は恵まれていた。一方で、
- メッシー君(外食の財布代わり、女性に食事を貢ぐ役割の男性)
- アッシー君(移動の足替わり、配車に応じる役割の男性)
- ミツグ君(買い物の財布代わり、女性の欲するものを貢ぐ役割の男性)
などと呼ばれる、若者女性の要望に応えるだけ、つまり経済的に搾取されるだけの若者男性が存在していた。経済状態だけでなく、社会的な状態も悪くはなかったとはいえ、彼らが本質的に「幸福」だったとは、私には思えない。とはいえ、その経験がトラウマ的に心に傷を残すことはなく、むしろ思い出、笑い話にできる程度には、気分はそれほど悪くはなかったのではないか、とも思うのだ。
人それぞれの幸福、不幸の決め手や尺度は分からないのだから、それらを一定に論じることはできない。各人においては、そのような漠然とした概念としての幸福、不幸を意識するのではなく、毎日の締めくくりに、今日は良い一日だった、と思える日を可能な限り増やすこと、増えること、そのような毎日が可能な限り継続すること、そのような状態、状況を維持できるよう、意識する方が、幸福/不幸を意識するよりも良いのではないか。
境遇の幸、不幸はともかく、各人にとっての「良い一日」が増えるならば、本質的に不幸である状況、認識は変わらないとしても、悪くない気分で過ごせる日は増えるのではないだろうか。