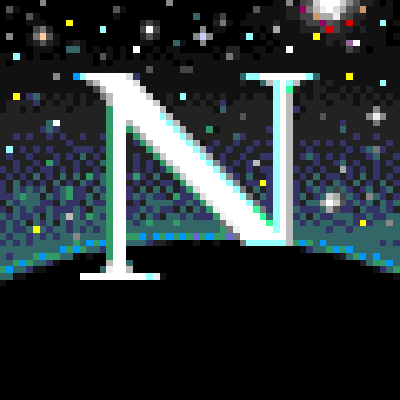
AIが人間を超えることってあるのだろうか。
既に物理的な制約は超えられている。たとえば計算速度だ。
とはいえ飛翔能力だって、走る速さだって動物に劣っているのだし。
人間が優れているのは、おそらく知能以外の何かだよ。
ビル・ゲイツにとって、現在の生成AIはGUI以来の革命的技術なのだそうだ。そして彼の慈善事業において、AIがどのように世界最悪の不公正を縮小出来るかを考えているのだという。しかし今回は、Windowsの時と趣が異なっている。
かつてビル・ゲイツは「A computer in every home and on every desk.」と言っていたように、一人一人の個人にコンピュータを使わせようとしていた。今回は、一人一人の個人がAIを使うというよりも、AIを適用することにフォーカスしていることだ。co-pilotやパーソナル・エージェントのように、ユーザー個人が利用する形態も想定しているのだが、それは生産性についてだ。おそらく慈善事業という背景によるところなのだろうが、それ以上に社会的な適用を意図している節がある。具体的には医療、教育、気候変動への適用だ。
ここで「AI」と呼ばれているものは、Chat GPTのような現在話題にされている「AI」を指している。それは、これまでSFなどで想像され「AI」と呼称されていたものとはことなるものだ。ちなみに、これまでの「AI」は「AGI」と呼称され、それはまだ実現していない。
ビル・ゲイツは、AIとAGIの違いを次のように定義している。
| AI | モデル | 特定の問題を解決するためのモデル 特定のサービスを提供するためのモデル 特定のタスクを学ぶことはできるが、他のタスクを学ぶことができない |
| AGI | ソフトウェア | どのようなタスク、課題も学ぶことができるソフトウェア |
生産性
AIによる生産性の向上については、ほぼ一般論だ。ポインティング・デバイスによる操作がタッチ操作に変化し、さらに自然言語による操作に代わろうとしている。
人はAIによって雑務から解放されるというのだが、これは眉唾だ。同じことはかつて何度も言われてきて、それらが現実になった試しは一度もない。ITによる効率化で人間はより人間らしい活動に取り組むと言われていたが、余計に忙しくなったばかりでなく、デジタル・デバイドから経済格差まで、諸々の格差が具現化し、拡大した。
AIにより効率化された業務の代わりに、また別の新たな業務が上乗せされるだけだろう。
教育
教育への適用にはグレー・ゾーン的な要素を感じる。学習者に応じたカスタマイズ教育は一般論だが、モチベーション管理にまで踏み込んでいる。飽きてきた頃合いをみて動機付けするのだろうだ。
理解や進展に応じてコンテンツの提供方法を変えるのは理解できるのだが、結果として「義務教育」が前提とする一律共通の知見を備えさせることができるのだろうか。現在は明らかにできていないが、AIでそれが可能になるのであればともかく、さらに格差が広がるだけのような気がしてならない。
さらに動機付けの問題は、生産性の面においては効果的なのだろうが、これは主従が逆転してはいないだろうか?
リスク
最後にリスクについて触れている。
人間の能力、特に物理的な制約を伴う能力限界をAIが超えるとき、AIの方がより優れた立場に到達するという可能性はあるかもしれない。一方、それが劣った存在に生み出されたのだから、物理的な制約を上回っただけで、行きつく先は人間もAIも同じ、という可能性もあるだろう。
もし後者だとすれば、現時点の人間からすれば利益相反、理解不能な目標であったとしても、それは時間をかければ理解できることだろう。つまり現在の人間が劣っているのではなく、ただ時間が足りないだけ、AIほど高速に処理できないだけ、という状況はあるかもしれない。
そこで一度AIを止め、理解できるまで考える、という手立てはあるはずだ。結局、利益相反、目標が理解できなくてもAIを止めることになるのだから。
用語
| AI | Artificial Intelligence | 現在話題になっている「AI」 |
| AGI | Artificial General Intelligence | 昔からSFなどで想像されている、いわゆる「AI」 |
| regurgitate | 吐き出す 繰り返す、反復する |
食べたものを吐き出す、オウム返しするような、何も意味を考えず、単純に与えられたものを出力するニュアンス |